|
学習会「消費者から見た機能性表示食品」
〜紅麹問題で制度はどう変わっていくか〜 を開催しました
紅麹のサプリメントによる健康被害問題を受けて、機能性表示食品制度が見直され、健康被害情報の収集と報告を義務づけることなどを盛り込んだ「食品表示基準の改正」が行われました。今後制度はどのように変わり、消費者はどのように受け止めて対応するべきなのか、これまでの経過や、検討会での論点などを振り返りながら、機能性表示食品制度の在り方について学び、消費者の目線で考えるための学習会を開催しました。
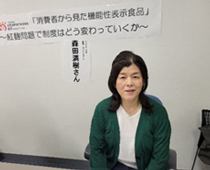
【日 時】7月25日(木)14時〜16時
〔Zoomによるオンライン学習会〕
【参加者】105名
【内 容】消費者から見た機能性表示食品
〜紅麹問題で制度はどう変わっていくか〜
【講 師】(一社) Food Communication Compass 代表
森田 満樹 さん(消費生活コンサルタント)
概要(事務局による要約)
Ⅰ、小林製薬の紅麹サプリメントをめぐる経緯
《小林製薬の対応と社会の動き》
- 小林製薬が自主回収を発表したのは3月22日ですが、最初に健康被害が疑われる報告があったとされるのは1月15日で、報告から発表までには2か月余りかかっています。同社は報告の時点では「健康食品が原因となった可能性があるとはわからず調査に時間がかかった」としています。
- また小林製薬は、3月29日の第2回記者会見までにで5例の死亡事例を公表しましたが、これ以降の死亡者の報告はありませんでした。その後6月28日になって76事例を報告し、問合せ170事例があったことが明らかになりました。
- この紅麹問題は、死者・入院患者数を含め、これまでの健康食品による事故では類を見ないほどの大きな問題になり、政府(厚労省・消費者庁)が原因究明と対策に乗り出しました。
- 3月22日の第1回記者会見直後、ベニコウジ色素への風評被害が拡大しました。紅麹原料(食品)とベニコウジ色素(食品添加物)とは培養方法も規格も違うものですが、消費者には紅麹サプリメントだけではなく、紅麹と名前の付く色々なもの(風味原料や添加物など)に不安が波及し、サプリメント全体の風評被害にもつながりました。
《政府の動き》
- 政府の対応は早く、消費者庁は3月26日に約7000件の全ての機能性表示食品の安全性確認について緊急点検を実施すると発表し、厚生労働省は小林製薬が直接原料を卸した52社と、これらの会社から原料を入手した173社の社名を公表して自主点検を求めました。
- 調査の結果、回収命令の対象となった3製品以外は特に問題はないことを政府は4月5日に発表しましたが、小林製薬の紅麹原料を使っている食品は数多く存在し、すでに自主回収や店頭告知の対応が行われていたこともあって、食品メーカーや社会全体にも大きな影響を及ぼす結果になりました。
- 全ての自主回収の情報は、厚生労働省のwebサイトで公表されていますが、紅麹関連商品の自主回収は3月末に相次いだという結果になります。
- 3月29日に開催された政府の関係閣僚会合では、健康被害情報の収集体制の見直しを含め、機能性表示食品の制度のあり方についての見直しを5月末までに行い取りまとめをする指示が出されました。この紅麹問題は工場の品質管理に問題があった結果起こったものですが、詳細な原因がわからない中、紅麹サプリが機能性表示食品であったために、ジャンルとしての機能性表示食品とその制度への批判が相次ぎました。それらを受け、消費者庁は制度の見直しに着手し、厚労省は原因究明等の対策を進めました。
- 消費者庁は「機能性表示食品を巡る検討会」を4月19日〜5月23日まで全6回行い、その議論の内容と報告書を5月27日に公表しました。その後6〜7月にかけて諮問機関である内閣府消費者委員会、および食品表示部会において「食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)に係る審議」が行われ、7月16日の消費者委員会において「諮問された改正案のとおりとすることが適当」とする答申書と、サプリメント食品全体について法整備を進めることなどを求める意見書が公表されました。このように短期間で機能性表示食品の制度改正の方向性が出され、改正に向けた手続きが行われました。
《原因究明の動き》
- 大阪市と日本腎臓学会の調査によると、紅麹サプリの摂取から短い期間で健康被害を発症したケースが多く見られ、毒性の強さが窺われると共に、小林製薬の報告や回収が少しでも早く行われていたら被害状況を少なく抑え込めたことが推察されます。原因究明については引き続き専門機関で継続されています。
- 原因物質はプベルル酸と言われてきましたが、工場内の青カビが、紅麹菌との共培養により、モナコリンKを修飾して化合物Y、Zが生成されたのではないかと考えられていますが、原因物質の特定と全容解明には、まだ時間がかかりそうです。
Ⅱ、機能性表示食品の制度改正
-
5月27日に公表された「機能性表示食品を巡る検討会報告書」等を受けて、5月31日に「ベニコウジ関連製品への対応に関する関係閣僚会合」で今後の対応が示されました。主な内容と論点は次のように整理されています。
- (1)健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等 = 健康被害情報の義務化を規定すること。
- 「食品表示法」に基づく表示基準の中で健康被害情報の収集を明確化することと、「食品衛生法」の施行規則に盛り込むこと、この2つの法律の「基準」と「施行規則」改正によって明確化することになります。両方とも改正内容について6月27日から30日間のパブリックコメントが行われました。
- (2)製造管理及び品質管理等 = サプリメント形状の加工食品の製造工程管理についてGMP(適正製造規範)を義務化すること。
- 機能性表示食品でもサプリメント形状の加工食品においては、GMPの要件化を食品表示基準の遵守事項とするとされました。なおGMP義務化については「製造」におけるGMPだけではなく「原料」の安全性に関する衛生管理についても検討会で問題視されました。原料の全てがGPMの要件に当てはまるものではありませんが、自主点検の見地から、今後は原料についても食品衛生法上での告示が行われる予定です。
- (3)機能性表示食品に関する情報提供の在り方 = 容器包装上の安全性に関する義務表示事項の表示に当たっては、表示の方法や方式の改善が必要であること。
- 「医薬品ではない」「特定保健用食品とは異なる」「医薬品、他成分との相互作用」などの表示方法が変わることになります。他にも容器包装上の「抜き書き」や「切り出し」により消費者の誤認を招かないようにとの観点から、消費者委員会の答申書の附帯意見には「義務的表示事項の機能性の届出範囲を逸脱する強調表示に対する規制を厳格化すべき」という内容が付されています。
- (4)その他
- 新規の機能性関与成分については、医学・薬学の専門家の意見を聞く仕組みを導入することのほか、消費者庁が届出資料をより慎重に確認するための特例措置として、届出資料の提出期限を販売日の60日間(通常)から120日間に延ばす規定が設けられることになりました。これにより新規の機能性表示食品のハードルが上がることになります。
- 事業者は届出時の規定を遵守していることを定期的(1年に1回)に自己評価し、その結果を消費者庁に報告することが義務付けられました。報告をしない場合は機能性表示ができなくなる場合があります。
- 他にも様々な改正が行われ、機能性表示食品は、小林製薬の紅麹サプリメントの問題を受けて、届出のハードルが上がり、その後の報告などについても規制が強化されることになりました。小林製薬の工場の製造管理の不備により多くの人の健康被害を招きましたが、このことによって食品衛生法、食品表示法の改正につながる結果になりました。
以上
≫ 開催案内はこちら
|